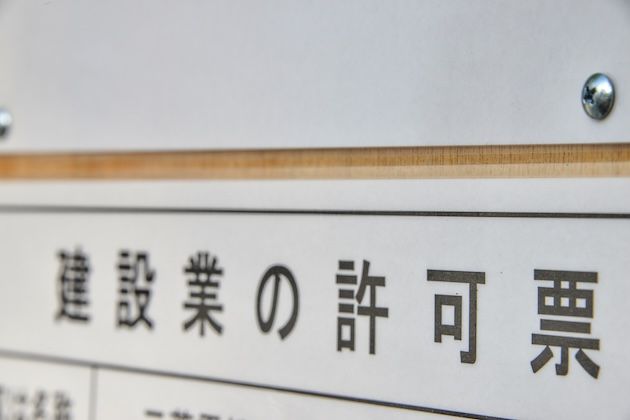NEWS
建築物衛生法とは?空気環境の基準や空調設備について解説
2025.07.25 空調機器活用ノウハウ

ビルやオフィスビルの管理に関わる方なら、「建築物衛生法」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、実際にどんな施設が対象で、どのような管理義務があるのかまで把握している方はそう多くありません。
この法律は、主に室内空気の質や衛生的な環境の維持を目的としており、空調設備や空気環境の定期的な測定が義務づけられるケースもあります。
この記事では、建築物衛生法の基本的な内容から、関連するビル管理法との違い、具体的な管理項目や設備基準までを、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
目次
建築物衛生法とは

建築物衛生法は、正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と呼ばれています。
この法律の目的は、不特定多数の人が利用する建物の室内環境を清潔かつ安全に保つことです。
空気の質、換気、清掃、給排水、照明、害虫などの管理を通じて、利用者の健康や快適性を守ることを目指しています。
適用対象となる施設の概要
この法律は、多くの人が利用する施設での衛生環境を守るためのものです。
具体的には、オフィスビル、商業施設、学校、病院など不特定多数が出入りする建物が対象となります。
この法律が定められた背景には、高度経済成長期以降の都市化により、大型のビルや商業施設が急増したことがあります。
これらの密閉空間では、空気の循環不足やホコリ・カビ・有害物質の滞留などが健康被害を引き起こすケースが見られ、「シックビル症候群」への社会的な関心が高まったことも法整備のきっかけとなりました。
なぜこのような法律が必要かというと、密閉された建物内では、空気の汚れや設備の不具合が放置されると、健康被害や衛生リスクにつながるからです。
法律では、延べ床面積が3,000㎡以上の施設を「特定建築物」と定義し、これらに対して定期的な空気環境の測定や設備管理を義務づけています。
建築物衛生法(ビル管法)とは

建築物衛生法、通称「ビル管法」とは、多数の人が利用する建築物の衛生的な環境を維持・管理するために定められた法律です。
正式名称は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で、厚生労働省が管轄しています。
この法律は、空気・水・清掃など建物内の環境衛生を守るための基準や義務を明文化し、快適かつ安全な建物管理を実現することを目的としています。
対象となるのは、事務所や学校、商業施設、病院など、不特定多数が利用する一定規模以上の建築物です。
建物の所有者や管理者に対して、専門的な清掃・空気環境の測定・水質管理などの実施義務が課せられる点が特徴です。
法的な適用範囲
ビル管法が適用される建築物には明確な基準があり、「延べ床面積3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)」の多数利用建築物が対象となります。
これは「特定建築物」と呼ばれ、法律に基づいた衛生管理が義務付けられます。
たとえば、ショッピングモール、オフィスビル、駅ビル、病院、大型商業施設、大学などが典型例です。
一方、これらの基準に満たない建物であっても、行政が必要と判断した場合には、例外的に「特定建築物」として扱われることもあります。
さらに特定建築物の管理者には空気環境の測定、給水設備の定期清掃、排水槽の保守、害虫防除、清掃などの業務を、一定の資格を有する「建築物環境衛生管理技術者」の指導のもとで実施することが求められます。
これにより、利用者の健康と快適性が法的に保たれる仕組みになっています。
特定建築物とは

建築物衛生法においては、特に厳しい管理が求められる建物を「特定建築物」と定義しています。
その定義や具体例、管理者に課される義務について見ていきましょう。
特定建築物の定義と基準
「特定建築物」とは延べ床面積が3,000㎡以上の建物で、かつ不特定多数の人が利用する施設を指します。
ただし学校や病院などの一部施設では、床面積が8,000㎡未満でも該当するケースもあります。
この区分が重要な理由は、特定建築物に該当すると、空気環境の定期測定や維持管理記録の保存が義務化されるためです。
特定建築物に該当する具体例
たとえば、以下のような施設が特定建築物に該当します。
- 延べ床面積5,000㎡のオフィスビル
- 大型ショッピングモール
- 総合病院(8,000㎡未満でも条件により該当)
- 大学や専門学校の校舎群
中小規模の事業所は該当しないこともありますが、規模拡張や用途変更の際には再確認が必要です。
届出や管理義務の内容
特定建築物に該当する場合、施設の管理者は保健所などの行政機関に届出を行い、「建築物環境衛生管理技術者」を選任する義務があります。
加えて、空気環境や給排水設備、清掃状態の記録を定期的に作成・保存しなければなりません。
もし届出や選任を怠った場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
空気環境の基準値

建築物衛生法では、室内空間の空気環境について具体的な測定基準が定められています。
測定項目とその基準値、測定・点検方法、記録や報告の実務について解説します。
空気環境の主要測定項目
法律により特定建築物では定期的に以下の6項目について空気環境の測定を行う必要があります。
| 測定項目 | 基準値 |
|---|---|
| 二酸化炭素(CO₂) | 1,000ppm以下 |
| 一酸化炭素(CO) | 10ppm以下 |
| 温度 | 17〜28℃(季節に応じて) |
| 相対湿度 | 40〜70% |
| 気流 | 0.5m/s以下 |
| 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 |
これらは、作業者や利用者の快適性・健康維持のために定められています。
たとえば、CO₂濃度が高いと眠気や集中力の低下を引き起こす恐れがあり、換気不足のサインとも言えます。
測定と点検の方法
空気環境の測定は原則として、おおむね2ヶ月ごとに1回以上の頻度で実施する必要があり、建築物環境衛生管理技術者または外部の測定業者が依頼することが多いです。
測定する場所についても注意が必要で、空調の吹き出し口付近や人の動きが少ない場所では正確なデータが得られにくいため、執務スペースの中央付近など代表的な位置での測定が推奨されています。
空気環境の記録・報告義務
測定した数値は、記録簿(環境測定記録)として保存する必要があります。
保存期間は3年間と定められており、保健所の立入検査などで提出を求められることがあります。
さらに、基準値を超える項目があった場合には、速やかに改善措置を講じ、その対応内容も記録しておくことが求められます。
たとえば、CO₂濃度が基準を超えた場合は、換気量の増加や空調設備の点検などが必要です。
空調設備に求められる基準

快適で衛生的な空気環境を保つためには、空調設備そのものの性能や設置条件も重要です。
ここでは、空調設備に対して求められる基準や注意点を解説します。
設置環境に適した性能と換気量
建築物衛生法では、空調設備の能力について明確な基準は定めていないものの、室内の空気環境基準を満たせる性能でなければなりません。
つまり、法令で求められる空気の質を保てることが前提条件です。
とくに重要なのが換気量です。人の出入りが多いオフィスや商業施設では、外気の取り入れ不足によりCO₂濃度が上がりやすいため、高機能な換気設備の導入が推奨されます。
設備ごとの注意点
空調設備には、パッケージエアコンやセントラル空調などさまざまな種類があります。
管理者としては、それぞれの設備に応じたメンテナンスが求められます。
たとえばセントラル空調の場合、ダクト内の汚れやフィルターの詰まりが原因で効率が落ちることがあり、年1回以上の清掃・点検が義務付けられている場合もあります。
一方で、個別エアコンでは熱交換器のカビや結露水の処理などにも注意が必要です。
建築物環境衛生管理基準の位置づけ

空気環境や設備の管理に関して、法律を具体化するものが「建築物環境衛生管理基準」です。
ここでは、この基準の背景や内容について説明します。
基準の策定背景と目的
この基準は、厚生労働省が建築物衛生法に基づいて定めたもので、全国の建築物管理者が準拠すべき共通ルールとして位置づけられています。
1990年代以降、シックハウス症候群やアスベスト問題など、室内空気に関する社会問題が注目されたことを受けて、内容が強化・見直されてきました。
基準の目的は、誰が管理しても一定水準以上の衛生状態が保てるようにすることにあります。
管理基準における主な項目
この管理基準には、次のような項目が定められています。
- 空気環境の維持(温度・湿度・気流など)
- 飲料水の衛生管理
- 排水設備の衛生管理
- 清掃状況の管理(床面・トイレなど)
- 害虫等の防除
つまり空調だけでなく、建物全体の衛生管理体制に関わる内容が含まれており、施設全体としての「清潔さと安全性」を確保するためのガイドラインと言えます。
よくある法令違反と対策

ここでは、実際に現場でよく見られる法令違反の例とその防止策について解説します。
知らないうちに違反しているケースも多いため、注意が必要です。
見落としやすい違反
たとえば、次のようなケースはよくある違反事例です。
- 空気環境の測定記録が未実施または紛失している
- 建築物環境衛生管理技術者が未選任
- ダクト清掃や空調機点検が規定より長期間未実施
- 届出義務のある変更(用途変更など)を報告していない
これらは意図的ではなく「知らなかった」が理由で起こる違反が大半です。
罰則や行政指導の可能性
違反内容によっては、保健所からの文書指導や立入検査の対象となります。
重大な違反が繰り返される場合には、改善命令や50万円以下の罰金が科されることもあります。
そのためにも、日頃から管理台帳を整備し、年次スケジュールで法令対応のチェックリストを作成しておくと安心です。
建築物衛生法に関するよくある質問
特定建築物に該当するか確認するには?
延べ床面積や施設の用途により該当の可否が決まります。
最寄りの保健所や行政窓口に図面や用途説明を持参して相談するのが確実です。
空気環境の測定は誰が行うのか?
原則として「建築物環境衛生管理技術者」が管理します。
実務は外部の測定業者に委託することも多く、報告書を受け取り記録する流れです。
空調設備の更新は義務か任意か?
法律では「更新義務」は明文化されていませんが、基準を満たせない場合には修繕や交換が必要です。
基準違反が続けば行政指導の対象になります。
衛生法とビル管法、どちらを優先すべきか?
両者は同一法であり、呼称の違いです。
混乱しないよう「建築物衛生法=正式名称」「ビル管法=現場用語」と理解して問題ありません。
小規模なオフィスでも届出は必要か?
延べ床面積が3,000㎡未満であれば、届出義務の対象外となることが多いです。
ただし、複数施設の合算や特殊用途(医療・学校など)では例外があるため確認が必要です。
まとめ
建築物衛生法は、施設を利用するすべての人の健康と快適性を守るために制定された法律です。
空気環境の測定、空調設備の点検、定期的な記録と報告など、管理者には多くの責任が課せられています。違反の多くは「知らなかった」から起こるものです。
法令や基準をしっかり理解し、必要な体制を整えることで、施設全体の衛生レベルが保たれ、利用者や従業員の信頼にもつながります。
オーソリティー空調では、商業施設やビルなどの空調・換気設備の設計から、施工、そして定期的なメンテナンスまで一貫して承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。