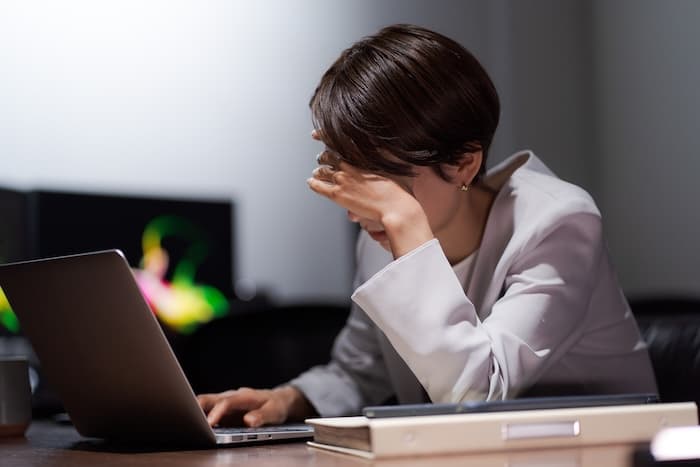NEWS
シックビル症候群とは?原因と対策、シックハウスとの違いを解説
2025.08.08 空調機器導入ノウハウ
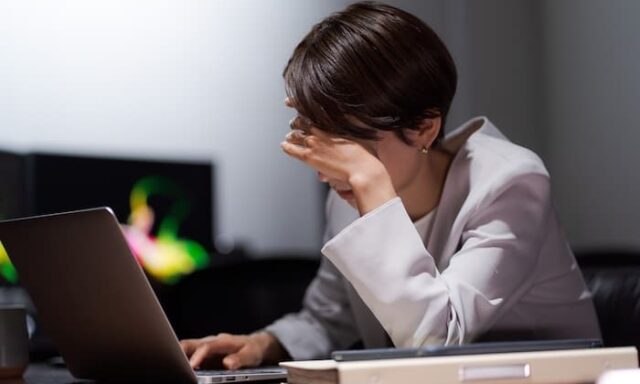
- ・汚れにくい家具選定と、集中を妨げない適切な距離感の座席配置が不可欠。
- ・ターゲットに合わせた本の選定と、それに連動したインテリアデザインが集客の鍵。
- ・重量物である本棚の固定や、飲食店としての衛生基準・防火基準の遵守が必須。
- ・本の閲覧動線とスタッフの配膳動線を分離し、サービス品質を維持する設計が必要。
いつも同じオフィスにいるのになぜか頭が重い、目がチカチカする、喉がイガイガするなど体の不調を感じながらも、気のせいだと思ってやり過ごしている人は少なくありません。しかし、それはシックビル症候群と呼ばれる空気環境が原因の健康障害かもしれません。
働く人の多くがビル内で一日を過ごす現代において、空気の質は働きやすさや健康と直結しています。この記事ではシックビル症候群とは何か、その原因や対策、そしてシックハウス症候群との違いを解説します。
シックビル症候群とは

1980年代以降、密閉性が高まり換気の少ない高層ビルで多く報告されるようになりました。
シックビル症候群の主な症状
頭痛、目の乾燥やかゆみ、喉の痛み、皮膚のかぶれ、倦怠感などが代表的です。特に午後以降になると症状が出る、ビルを出ると改善する場合は空気環境が原因と考えられます。
発症しやすい建物や空間の特徴
窓が開かない高層オフィスビル、商業施設、換気設備が不十分な場所で発症例が多く見られます。とくに新築や改装直後のビルでは、揮発性の物質が多く空気中に残っている場合があり注意が必要です。
シックハウス症候群との違い
シックハウス症候群は主に住宅で発生する健康障害を指し、原因や症状は似ていますが対象の建物や法規制が異なります。
シックビル症候群とシックハウス症候群の比較表
| 項目 | シックビル症候群 | シックハウス症候群 |
|---|---|---|
| 対象建物 | オフィスビル・商業施設等 | 住宅(戸建て・集合住宅) |
| 主な原因 | 換気不足、建材、VOC、空調の問題 | 建材、家具、VOC、ホルムアルデヒド |
| 主な症状 | 頭痛、目や喉の刺激、疲労感など | 鼻炎、咳、喘息、皮膚炎など |
| 規制・対策 | ビル管理法、厚労省指針など | 建築基準法(ホルムアルデヒド等の制限) |
| 法的な責任 | 管理者責任が問われるケースもあり | 施工者や販売者の責任が問われることも |
シックビル症候群の原因

シックビル症候群は1つの明確な原因ではなく、複数の環境要因が重なって発症するケースが大半です。とくに揮発性化学物質や換気不良、内装材の影響はよく知られており、日常的な環境管理の見直しが重要です。
揮発性有機化合物(VOC)とホルムアルデヒド
内装や家具に使われる接着剤・塗料から放出される化学物質が、空気中に長時間漂うことがあります。中でも有名なのがホルムアルデヒド。目や喉を刺激するだけでなく、発がん性の疑いも指摘されています。
このような物質は「揮発性有機化合物(VOC)」と総称され、環境省や厚労省も指針値を定めています。特に新築やリノベーション直後は濃度が高まりやすく、換気が不十分な場合は長期間にわたり人体に影響を与える恐れがあります。
換気不良や空調の問題
どんなに良い建材を使っていても、空気が循環せずにこもってしまえば化学物質や湿気が蓄積されていきます。換気設備が古かったり、使用頻度が低いスペースでは、二酸化炭素濃度の上昇やカビの発生も重なり、体調不良につながります。
実際、厚生労働省の「建築物衛生法(ビル管理法)」でも、二酸化炭素やホルムアルデヒドの濃度について基準値が定められており換気設備の定期点検が義務化されています。
建材・家具・内装素材の影響
シックビル症候群の原因は目に見えない空気だけでなく、建物そのものに潜んでいます。たとえば、床や壁紙、天井に使われる合板や塗料。これらが揮発性の物質を発し続けることで、時間の経過とともに空気を汚染してしまうのです。
また机や椅子、収納棚などの家具も見落としがちですが、接着剤や塗装剤の選定次第で空気環境に影響を及ぼすため、素材の選び方には注意が必要です。
参考記事:“F☆☆☆☆マーク”の意味は?読み方やシックハウスなどの空気環境について解説
健康被害と診断のポイント

シックビル症候群の厄介な点は「なんとなく体調が悪い」という曖昧な症状が多く、診断や対策が遅れがちになることです。症状の具体例や相談先を知っておくことで、早期発見・対応につながります。
よくある初期症状と重症化リスク
典型的な初期症状は目や喉の乾燥、頭痛、倦怠感など。風邪やストレスと勘違いしやすく、職場の空気が原因だと気づかないまま症状が慢性化するケースもあります。特に注意が必要なのは呼吸器系への影響が進行した場合。喘息や気管支炎、皮膚の炎症など、慢性的な疾患につながることも報告されています。
子どもや高齢者、アレルギー体質の人は影響を受けやすいため、早めの対応が肝心です。
病院での診断と対応方法
一般的な内科では診断が難しい場合もあるため、「環境アレルギー外来」や「職業病外来」など、専門の診療科を受診するのがおすすめです。問診のほか、空気中の化学物質濃度の調査や血液検査などを組み合わせて判断されます。
また、勤務先や住環境に関する情報を記録しておくと、原因特定の手がかりになります。
症状が出た時間帯や場所、発症から改善までの経過をメモしておくと役立ちます。
被害が疑われるときの相談窓口
厚生労働省や各自治体では、建物内の空気環境に関する相談窓口を設けています。たとえば「都道府県労働局」や「環境保健センター」では、職場環境の調査や改善指導を依頼することが可能です。
また、社内の衛生委員会や安全衛生担当者にも相談し、ビル管理会社と連携して空気環境の点検・改善を働きかけるのが現実的なステップとなります。
シックビル症候群の対策方法

シックビル症候群への対策は、「原因の排除」と「継続的な空気環境の管理」が基本となります。空調・換気の見直しや、内装・家具の素材選定にまで目を向けることが、快適なオフィス空間づくりの第一歩です。
換気改善と空気質のモニタリング
最も基本的で効果的な対策は「十分な換気」です。とくに現代の高気密な建物では、空気がこもりやすく、有害物質が蓄積されるリスクが高くなります。一例として、二酸化炭素濃度を測定するモニターを設置すれば、換気が不十分な時間帯や空間が可視化できます。これにより、空調設備の稼働タイミングや人員配置の調整といった実用的な改善が可能になります。
また、空気清浄機の導入や換気扇の増設も有効です。重要なのは、「なんとなく体感で換気」ではなく、データに基づいた管理に切り替えることです。
内装材・家具の見直しとリスク低減
目に見えない空気中の化学物質は、内装や家具から長期間にわたり放出され続けることがあります。そのため、新規導入時やリフォーム時には「F☆☆☆☆(フォースター)」など、ホルムアルデヒド放散量の少ない建材・家具を選ぶことが推奨されます。
特に注意が必要なのが、化粧板、床材、カーペット、パーティションなどの貼り物や接着剤を使う素材。こうした素材を多用する空間では、施工時から空気環境に配慮することが求められます。
すでに設置済みの家具や内装についても、可能であれば表面の加工やカバー、レイアウト変更によってリスクを軽減できる場合があります。
ビル管理者が取るべき予防策
ビル全体の空気環境を維持するにはテナント任せではなく、建物管理者による主導的な対応が不可欠です。たとえば、建築物環境衛生管理基準では、空気環境の定期測定や清掃、設備保守などが義務付けられています。
具体的には以下のような取り組みが挙げられます。
- ・定期的な換気設備の点検と清掃
- ・空気環境測定(CO₂・ホルムアルデヒド濃度など)の実施
- ・清掃業務の標準化とマニュアル整備
- ・入居テナントへの情報共有・啓発活動
これらをルール化・文書化することで、入居者の安心感を高めるだけでなく法令遵守にもつながります。とくに近年ではESGやウェルビーイングの観点からも、環境配慮型ビルが選される傾向にあります。
法規制と基準
シックビル症候群は健康被害を引き起こす可能性があるため、国や自治体でもその対策として室内環境に関する法規制やガイドラインを整備しています。とくにオフィスビルや商業施設では、法的な管理義務を正しく理解し適切に対応することが求められます。
室内空気環境のガイドライン
厚生労働省では「建築物環境衛生管理基準」に基づき、ビル管理者が維持すべき空気環境の指針を提示しています。代表的な指標として、以下の項目が挙げられます。
- ・二酸化炭素(CO₂):1,000ppm以下
- ・ホルムアルデヒド:0.08ppm以下
- ・浮遊粉じん:0.15mg/㎥以下
- ・温度:17〜28℃
- ・湿度:40〜70%
これらの値を超えると不快感や健康リスクが高まり、労働生産性にも悪影響を与えかねません。とくにCO₂濃度の上昇は換気不良のシグナルであり、早急な対応が必要です。
定期的な測定と記録を行い、異常値が出た場合には迅速な改善を図る体制づくりが重要です。
シックハウス対策としての建築基準法の規制
住宅や小規模施設におけるシックハウス症候群への対策としては、2003年の建築基準法改正が大きな転機となりました。この改正によりホルムアルデヒドなどの有害物質の使用が制限され、以下のような規定が導入されました。
- ・ホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限(等級表示制度)
- ・原則として全居室に24時間換気設備の設置が義務化
これにより、新築物件におけるホルムアルデヒド暴露は大幅に低減されました。
しかし、既存の建物や内装リフォーム時には依然として注意が必要です。なお、オフィスビルなど非住宅用途についても同様の配慮が求められますが、厳格な施工管理は建物所有者やテナント側の自主性に委ねられている部分も多くあります。
ビル管理法における換気義務と環境基準
ビルや商業施設の空気環境を維持するうえで、重要な法律が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、通称「ビル管理法」です。
この法律では、延床面積3,000㎡以上の特定建築物に対し、空気環境測定や設備点検、清掃などの実施を義務づけています。この中で定められた環境基準に違反した場合、是正命令や指導の対象となることもあります。
したがって、ビル管理者は定期的な点検と記録の保存、専門業者による測定体制の構築が欠かせません。とくに新型コロナウイルスの大流行以降は、換気の重要性が再認識されておりビル管理法の基準以上に高いレベルの空気質管理が求められる場面も増えています。
よくある質問
シックビル症候群は誰でも発症するのか?
誰にでも発症する可能性はあります。ただし、体質や環境への感受性に個人差があるため、全員が同じ症状を訴えるわけではありません。
たとえば、化学物質過敏症のように微量な刺激でも不調を感じやすい人もいれば、まったく症状が出ない人もいます。特に子どもや高齢者、持病のある方は影響を受けやすいため、オフィスや施設を管理する側としては「症状の有無ではなく、予防と改善を重視する」ことが重要です。
シックビル症候群は一度発症すると治りづらい?
必ずしもそうではありません。原因となる環境要因を除去すれば、多くのケースで改善が期待できます。たとえば、オフィスの換気を改善したり、刺激の少ない建材・家具に入れ替えることで、数日〜数週間で症状が軽快する人もいます。
自宅でもシックビル症候群になるのか?
可能性はあります。住居における「シックハウス症候群」と非常に近いメカズムで発症するため注意が必要です。特にリフォーム直後、新築物件への引っ越し後、あるいは家具を新調した際などはホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)の濃度が高まりやすくなる傾向にあります。
24時間換気設備をきちんと稼働させ、空気清浄機を併用するなどの対策が推奨されます。
対策しても症状が改善しないときは?
症状が続く場合は、原因が空気環境以外にある可能性もあるため、まずは医療機関で診断を受け、必要に応じて職場環境の再評価や、専門業者による空気質調査を検討してみてください。
会社に改善を求めたい場合の対応は?
まずは上司や総務・施設管理部門に事実を伝え、環境測定や換気確認の実施を依頼するのが第一歩です。また労働安全衛生法に基づいて「労働者の健康保持」が義務づけられているため、状況によっては産業医や労働基準監督署に相談する選択肢もあります。
まとめ
シックビル症候群は、現代のオフィスや建築物に潜む「見えない健康リスク」ともいえる存在です。主な原因には、換気不足や内装素材から発生する化学物質(VOC、ホルムアルデヒドなど)があり、頭痛・倦怠感・めまいといった症状が現れることがあります。
特に近年は、ビルの高気密化や、作業効率を優先した設計が進む一方で、空気の質や換気の重要性が見落としがちです。しかし、建物利用者の健康や生産性に直結する問題である以上、「誰かの問題」ではなく「組織全体で向き合うべき課題」として捉えるべきでしょう。
すでに不調を訴える従業員がいる場合は、空気環境のチェックや専門家の調査を早急に行い、改善策を講じることが最優先です。また、今後の予防としても「内装材選び」「換気設備の見直し」「定期的な空気質モニタリング」は、ビル管理者やオーナーにとって不可欠な対応となります。
働く環境を整えることは、結果的に生産性や従業員満足度の向上にもつながります。今の職場環境に少しでも不安があるなら、この機会に「空気」という見えない資産に目を向けてみてはいかがでしょうか。
オーソリティー空調では換気設備を含む空調設備の設置・設計から、内装デザイン・施工工事を含む空間デザインをご提案させていただきます。空調設備のトータルコーディネートは、オーソリティー空調にぜひお任せください。